伊方町の学校では、原子力防災として屋内退避訓練があります。
本日の訓練では、地震が発生し、伊方原子力発電所3号機の原子炉が自動停止した後、原子炉が破損したことから、放射性物質の放出の危険性が高まったという想定です。
荷物をまとめて、屋内退避します。

校長先生から、37年前に起こったウクライナのチャルノブイリ原発事故と12年前の東日本大震災で起こった福島第一原発事故を例にとり、お話がありました。
ポイントは、「屋内へひきこもる」です。
 o
o
その後、更に詳しく知るためにDVDを視聴しました。
みんな真剣な表情で見ていました。
是非、御家庭においても話し合ってみてください。

10月8日、日曜日。
秋雨の降る中、大久の秋祭りが行われました。
浜には幟が立ち並び、四ツ太鼓の音が響き渡ります。

天狗がお神輿を先導します。

お神輿の後に、四ツ太鼓。小学生が4人元気よく太鼓をたたきます。

一番最後に練り歩くのが、牛鬼。
小学生から高校生までが担ぎ手。
子どもたちみんなが関わることができる祭りとなっています。

神事が終わったら、主役である四ツ太鼓をたたいた子どもたちは、足が地につかないよう、大切に肩車され帰って行きます。
未来に残したいふるさとの風景です。
文化の秋。子どもたちの活躍がすごい!
西宇和郡健康に関する作文審査において、4年生Yさんが特選。

5年生MさんとAさんが佳作。


自分で考えて健康な体を作っていこうとする取組。家族への温かい思いや協力もありました。
それらが、明るい笑顔につながっているのだと感じます。
80・20運動とは、歯磨きをしっかりして
「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」
という運動です。
10月3日(火)の2校時目に、歯磨き教室をしました。コロナ禍でしばらく実施していなかったこともあり、2年生たちは、初めてカラーテスターを体験しました。
はじめ、歯科衛生士の方に、なぜ虫歯になるかについて教えていただきました。


その後、カラーテスターを歯に塗ってもらいました。
「赤い色のところが汚れているところですよ。」
と聞いて、子どもたちはびっくり。
予想以上に赤く染まった自分の歯を見て、日頃の磨き方を振り返ることができました。


歯科衛生士の方曰く、「フッ素洗口をしても、きちんと磨いていなければ効果は薄い。」とのことです。


そして、「低学年は磨き残しがあるので、家庭で、仕上げ磨きをぜひしてもらってください。」
とも言われていましたので、ご家庭でもよろしくお願いします。
毎月2回程度の将棋教室が、2名のボランティアによって開かれています。それを楽しみにしている子どもたちもいます。本日は、6名の参加。全校の3分の1ですから、すごい割合です。





運動場では、ブランコに乗ったり、追いかけっこをしたり。
子どもたちは、自分にあった楽しみを見つけ、好奇心を育んでいます。
9月29日(金)は中秋の名月。
朝から子どもたちの間でも話題になっていました。
給食では、お月見メニューが出され、おいしくいただきました。
伊方町の給食は、おいしい!


太陽が別れを告げる頃、西の空が夕焼けで染まっていきます。
ひこうき雲がとてもきれいでした。

そして、交代で月が東から昇ってきます。
月明りに照らされた宇和海には、月明りの道ができました。
子どもたちも、それぞれの家庭で中秋の名月を楽しんだことでしょう。

伊方町は俳句のまちづくりを進めています。
伊方町九町出身で、有名な俳人坪内稔典さんがいます。
ここで一句
青岬そのてっぺんのミュージアム 坪内 稔典
広報いかた10月号に、第4回佐田岬トーク(投句)の入選者が掲載されました。
大久小学校でも俳句づくりを楽しんでいます。何と10点のうち2名も入選しました。
★ 夏の昼宿題中に波の音 5年NAさん
宿題時のBGMが波の音とは、何ともうらやましい環境です。

★ かまきりの赤ちゃんかべに一じかん 2年NSさん
NSさんは、よほど生き物が好きなようです。1時間も見ていたなんて。この好奇心がすごい!
子どもたちの学力アップと生きるための力を身に付けるために、教師の授業改善を進めています。
研究テーマは、「進んで学び、自分の考えを広げ深める児童の育成 ~他者との関わり・協働を通して~」
5・6年生で国語の研究授業を行いました。
研究のねらいは、「児童が主体的に学習する指導の工夫」

積極的に発表する児童に対して、内容の整理整頓を支援しています。
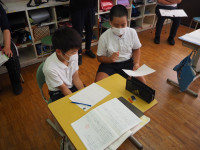

自分の考えをペアで伝え合います。

1つの教室で2つの学年が学習する複式授業ですから、隣の6年生は、伊方町の教育活動支援員のアドバイスで、文章をまとめています。
この研究授業の時間、他の学年は自習をしています。
プリント学習、タブレット学習、読書など教室に誰もいないと勘違いするくらい静かに、集中していました。
これは、本当にすごいことです。
自らが学ぶ姿勢を大切にしていきます。
文化の秋です。
51回目の歴史ある「えひめのクロッキー展」において多くの受賞がありました。
〇 特選 2年生3名 3年生1名




〇 入選 2年生2名 3年生2名 4年生1名





賞状授与のときの返事も大変力強く、喜びと自信に満ちていました。
o